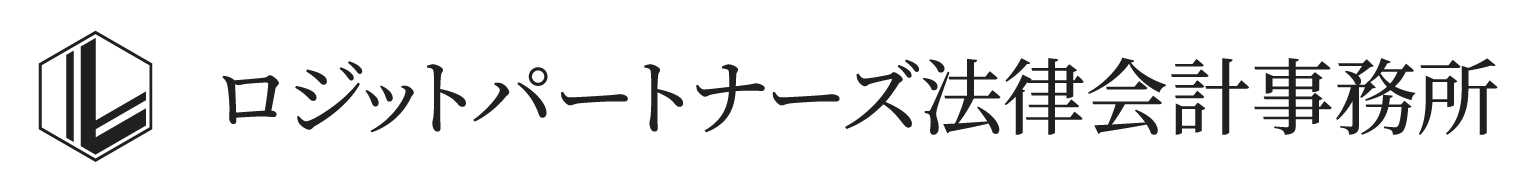障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から施行されます。
この改正により民間事業者も障害者への「合理的配慮の提供」を義務付けられることとなり、多くの企業に影響が及びます。概要を以下にまとめます。
Contents
障害者差別解消法とは
障害者差別解消法は、平成28年に施行された比較的新しい法律です。「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」(第1条)を目的としています。
障害者差別解消法が定める民間事業者の義務
障害者差別解消法は、民間事業者(「商業その他の事業を行うもの」)に対して以下の3つの義務を課しています。
不当な差別的取扱いの禁止(8条1項)
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
障害者差別解消法
第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
合理的配慮の提供(8条2項)
第八条 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
障害者差別解消法
環境の整備(第5条)
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
障害者差別解消法
第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
令和6年4月施行の改正
従前の障害者差別解消法は民間事業者について、「不当な差別的取扱いの禁止」は法的義務(しなければならない)とする一方、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」は努力義務(するよう務めなければならない)としていました。しかし令和6年4月施行の改正により、民間事業者による「合理的配慮の提供」が法的義務に格上げされます。
これにより全ての民間事業者が令和6年4月から新たな法的義務を当然に負うこととなります。極めて影響範囲の広い法改正といえます。
「合理的配慮」の内容
合理的配慮の提供が法的義務とされた以上、その内容を理解することが法令遵守の観点から極めて重要です。個別のケースにおける具体的な義務の内容が明確に法定されているわけではありませんが、以下の資料が解釈の指針となります。
- 内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
政府による障害者差別解消に関する基本方針です。合理的配慮の内容を検討する際にも出発点となります。 - 各関係省庁における対応指針
各関係省庁が、所管する事業者に対して指針を提供しています。各企業においては、自らの所管官庁が提供している対応指針の内容を把握しておくべきと考えられます。 - 内閣府 法改正リーフレット
令和6年4月改正について解説したリーフレットです。合理的配慮の内容についての具体例が記載されています。 - 内閣府 障害者差別解消に関する事例データベース
「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例を、障害種別などに応じて検索できるシステムです。 - 内閣府 合理的配慮等具体例データ集
合理的配慮の具体的な事例を紹介しているページです。 - デジタル庁 ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック
デジタル庁が公表しているウェブアクセシビリティ導入についてのガイドブックです。具体例が豊富に記載されており、BtoCウェブサイトの構築にあたっては参考になる資料です。
これらの資料を参考にしながら、自らの事業で発生することが考えられる具体的なケースにおいて、どの程度の対応であれば「負担が過重」でないかを検討し、現場での対応マニュアル等に落とし込んでいく作業が必要となります。
違反時の影響
「合理的配慮の提供」義務に違反した場合の影響として、以下が考えられます。
罰則
障害者差別解消法では、民間事業者が8条の義務に違反した場合について、以下のとおり規定しています。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
障害者差別解消法
すなわち、法的義務に違反した場合、所管官庁から報告を求められるおそれがあり、それに対して報告を懈怠したり虚偽の報告を行った場合に過料の制裁を受ける、という建付けになっています。
損害賠償請求
合理的配慮の提供が法的義務とされたことで、合理的配慮の提供を行わないことは違法行為となります。したがって、今後は民間事業者に対し、障害者差別解消法違反に基づく損害賠償請求(民法709条)がなされるケースが増加すると考えられます。民間事業者としては、基本的な対応方針を明確に定めたうえで、適切な請求に対しては真摯に対応し、不当な請求に対しては毅然と対応することが必要となります。
レピュテーションリスク
障害者差別解消法の改正に伴い、障害者差別に対する社会全体の感度も上がっていくと考えられます。個別の事案で適切な対応を取れなければ、SNS等で「差別企業」のレッテルを貼られるケースも考えられます。そういったリスクも考慮した上で、企業として対応可能な水準を検討する必要があります。
関係法令
障害者雇用促進法との関係
障害者差別解消法が施行された平成28年に障害者雇用促進法も大改正が行われ、「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」が義務化されています。詳細は別記事にて記載します。
各自治体の条例
各自治体においても障害者差別に関する条例を独自に制定しているケースが多いです。
当事務所が所在する東京都では、平成30年に東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例が施行されました。同条例では、民間事業者による合理的配慮の提供が義務化されており、障害者差別解消法の改正の先取りともいえます。罰則はありませんが、紛争が生じた場合に東京都が「あっせん」する制度が設けられており、「あっせん」で解決しない場合、知事からの是正勧告や事業者名の公表へとつながる制度設計となっています。
過去の実績では「あっせん」で解決したケースが2件あるのみで、是正勧告や公表の事例はありませんが、障害者差別解消法の改正に伴いこちらも制度活用が活発化する可能性があり、民間事業者としては留意が必要です。
ロジットパートナーズ法律会計事務所のサービス
これまで述べたとおり、今回の障害者差別解消法の改正は民間事業者に「合理的配慮の提供」という法的義務を新たに課すという、極めて影響範囲の広いものです。そして「合理的配慮」の内容について法令が必ずしも明確に定めていない以上、民間事業者としては、規程類の整備や教育研修等を通じて、企業として責任と自信をもって障害者対応ができる態勢を構築することが重要です。
当事務所では、企業法務を専門とする弁護士が、障害者対応に関する企業としての基本方針の検討、個別ケース分析、規程・マニュアル類の作成・管理、役職員への研修、有事の際の対応に至るまで、障害者差別解消法に関連するサポートを幅広く提供しています。
お気軽にお問合せください。