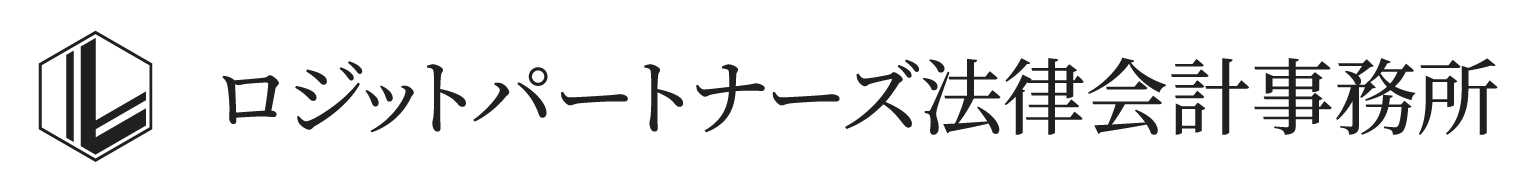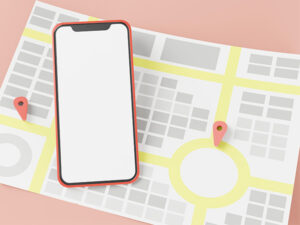令和6年度地価公示の結果が国土交通省より発表されました。
本記事では、当事務所が存する東京23区を中心に、地価公示結果の概要を紹介します。
Contents
地価公示制度とは
地価公示制度は地価公示法に基づく制度です。国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回、全国約26,000箇所の「標準地」の正常な価格を公示するものです。
価格評価の基準日は1月1日であり、毎年3月下旬に結果が公表されます。
令和6年度地価公示の結果概要
全国的な傾向
全国平均の変動率(前年比)は、住宅地+2.0%、商業地+3.1%、工業地+4.2%となりました。
過去のトレンドを見ると、令和3、4年度には新型コロナウイルス感染拡大の影響で下落に転じたポイントも多かったですが、その多くが令和5年度に上昇に転じました。今回(令和6年度)はその上昇トレンドがより強まったといえます。
圏域別にみると、ここ数年の傾向どおり、地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)の上昇率が顕著に高く、三大都市圏(東京、大阪、名古屋圏)を凌ぐ水準となっています。特に福岡市は住宅地+9.6%、商業地+12.6%と、地価の高い上昇が続いています。
東京圏の傾向
東京圏の変動率(前年比)は、住宅地+3.4%、商業地+5.6%、工業地+6.2%となりました。いずれも全国平均を2%ほど上回る上昇率であり、東京圏の土地価格の上昇スピードの速さを顕著に表す結果となったといえます。
東京23区の傾向
これを東京23区に絞ると、住宅地+5.4%、商業地+7.0%となり、上昇トレンドがより顕著です。
住宅地について上昇率が特に高かったのは、豊島区(+7.8%)、中央区(+7.5%)、文京区(+7.4%)、目黒区(+7.3%)、港区(+7.2%)等です。都心に隣接する通勤利便性が高い地域において、土地需要、特にマンション用地の需要が旺盛だったと考えられます。一方、その外縁に存する練馬区(+4.0%)や世田谷区(+4.0%)は比較的低い上昇率となりました。
一方、商業地について上昇率が特に高かったのは、台東区(+9.1%)、荒川区(+8.3%)、中野区(+8.2%)、杉並区(+8.0%)、豊島区(+8.0%)となっており、住宅地とは様相が異なります。台東区については、インバウンドの観光需要の回復により、浅草周辺エリアの商業地需要が旺盛であったと考えられます。
地価公示の影響
地価公示の結果は、企業や個人に様々な影響を与えます。以下はその例示です。
固定資産税・相続税への影響
固定資産税評価額及び相続税路線価は、公示地価の水準と連動して決定されます。一般に、固定資産税評価額は公示地価の7割、相続税路線価は公示地価の8割が相場と言われています。公示地価の上昇は、今後の固定資産税や相続税の増加につながる可能性が高く、土地の所有者や相続人は注意が必要です。
地代への影響
借地契約における継続地代の鑑定評価にあたっては、差額配分法、利回り法、スライド法等、様々な手法が用いられますが、いずれの手法でも公示地価の上昇は継続地代にプラスの影響を与えます。
土地所有者(地主)においては、地価公示における土地価格の上昇を考慮して、地代の増額請求を行うべきか積極的に検討すべきでしょう。反対に、公示地価の上昇幅の大きい地域に借地を持つ借地権者は、地主からの地代増額請求に備える必要があります。
家賃への影響
公示地価は建物ではなく土地の価格ですが、鑑定理論上、土地価格の上昇は正常家賃の水準にも影響を与えます。すなわち、家賃についても増額請求につながる可能性が考えられます。
(参考)不動産鑑定士による土地価格の鑑定評価と公示地価
不動産鑑定士による土地価格の鑑定評価においては、公示地価を「規準」とすべき旨が、国土交通省の不動産鑑定評価基準において定められています。
地価公示法施行規則第1条第1項に規定する国土交通大臣が定める公示区域において土地の正常価格を求めるときは、公示価格を規準としなければならない。
不動産鑑定評価基準
もっとも、実際の鑑定評価では、近隣の標準地の公示地価と乖離した評価額が出されることは珍しくありません。特に都心部の商業地では、公示地価と実際の取引価格の乖離が顕著と言われています。地価の分析をする際には、公示地価だけでなく実際の取引市場のデータも可能な限り参照すべきといえます。
地価調査とは
地価調査とは、各都道府県が毎年1回、全国約21,000箇所の「基準地」の正常な価格を評価し公表する制度です。地価公示法とは別の法律(国土利用計画法)によって定められている制度です。
土地の正常価格を公の機関が公示するという点では地価公示と似ていますが、重要な相違点として、地価調査は基準日が毎年7月1日とされています。地価公示とちょうど半年ずれているため、両者をうまく併用して地価のトレンドを分析するのが一般的です。特に、地価公示と地価調査の共通地点(約1,600箇所)では、半年ごとに連続して公の価格が公示されることとなるため、該当エリアにおける土地価格の趨勢分析に広く活用されています。
地価公示の分析に有用なサイト
地価公示・地価調査の結果の分析にあたっては、以下のサイトが有用です。令和6年度の結果も近日中に反映されると思われます。
- 標準地・基準地検索システム
国土交通省の提供するシステムです。地価公示・地価調査の各ポイントについて、不動産鑑定士が作成した実際の鑑定評価書をダウンロードすることができます。 - 東京都の地価
東京都不動産鑑定士協会が提供するツールです。
東京都だけでなく、全国の地価公示及び地価調査の結果を、昭和56年まで遡ってマップ上で確認することができます。 - 全国地価マップ
(一財)資産評価システム研究センターが提供するツールです。地価公示だけでなく、固定資産税路線価及び相続税路線価もマップ上で確認することができます。 - rpamap
検索機能に優れた公示地価マップです。
ロジットパートナーズ法律会計事務所のサービス
今回の地価公示の結果は、日本全国、特に三大都市圏や地方四市の都心部における土地価格の上昇トレンドが根強いことを明確に示したといえます。また、物価高や円安により、建物の建築コストや維持管理コストも上昇する一方です。コスト意識の強まりから、不動産所有者(賃貸人)による地代・家賃の増額請求や、賃貸借解除・立退等の紛争が増加する可能性が高いと考えられます。
当事務所は不動産鑑定士資格を有する弁護士が在籍しており、不動産の価格や賃料の評価についての紛争や訴訟に強みを持っています。また、当事務所には税理士・司法書士も在籍しており、不動産に係る税務や登記に波及する問題に対してもワンストップで対応可能です。
お気軽にお問合せください。