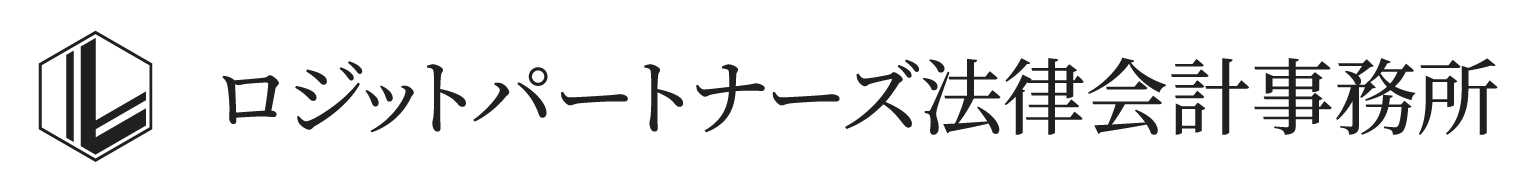土地価格の上昇に伴い、借地の地主の方から、現行の地代が不相当に低廉になったとご相談を受けることが増えています。
ここでは土地の賃料(地代)増額請求につき、概要を紹介します。
Contents
地代増額請求とは
借地借家法(又は旧借地法)により、借地契約は更新が原則とされています。そのため、特に契約開始時点が古い借地契約では、地代が低いまま更新が繰り返されているケースが多くみられます。
そのような状態を解消するために、借地借家法11条が地代増額請求について定めています。
地代増額請求が認められるための要件は、地代が「土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき」です。
第十一条 地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
借地借家法
地代増額請求の手続
交渉
最初のステップは当事者間の交渉です。地主と借地権者の関係が良好な場合、交渉により地代増額の合意に至るケースもあります。
合意に至らない場合、借地借家法に基づく地代増額請求を行うことになります。
増額請求
地代増額請求をすると、法的にはその時点から増額の効果が発生します。したがって、増額請求をした事実及びその時点を明確にするために、配達証明付内容証明郵便により増額請求を行うのが一般的です。
ただし、増額請求を受けた借地権者は、自身が「相当と認める」額を支払えば債務不履行とはなりません。地代が極めて低廉(公租公課を下回る場合等)を除いて、現行地代の支払えば基本的には問題ありません。
第十一条 2 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
借地借家法
調停
増額請求後に交渉が整わない場合、民事訴訟を提起する前に、まずは調停手続を経る必要があります(調停前置主義)。
第二十四条の二 借地借家法(平成三年法律第九十号)第十一条の地代若しくは土地の借賃の額の増減の請求又は同法第三十二条の建物の借賃の額の増減の請求に関する事件について訴えを提起しようとする者は、まず調停の申立てをしなければならない。
民事調停法
地代増額請求に係る調停の管轄は、原則として物件の所在地を管轄する簡易裁判所です。東京都の土地の場合、錦糸町の東京簡易裁判所墨田庁舎となります。通常の民事訴訟や調停と扱いが異なるため、注意が必要です。
訴訟提起
調停不成立となった場合、地主側から訴訟を提起することとなります。
賃料増額訴訟では、裁判所が鑑定人として不動産鑑定士を選任し、当該鑑定人が行った継続賃料の鑑定評価結果に基づいて判決が出されることが一般的です。したがって、両当事者は、鑑定人の鑑定結果を自らに有利にすべく、事実を主張し証拠を提出していくことになります。当事者側が自ら不動産鑑定士に鑑定を依頼し、その評価書を証拠提出することもあります。
注意点としては、鑑定人の鑑定費用の負担があります。これは通常、増額請求が認められた割合に基づいて原告と被告で按分して負担額を決定します。したがって、無理に高額な地代を請求しても、鑑定費用の負担割合が増えるだけに終わってしまうおそれがあります。もっとも、請求しなければ認められないのも事実ですので、最適な請求額を慎重に見極める必要があります。
継続賃料
地代増額請求がどの程度認められるかは、裁判所が選任した鑑定人による継続賃料の鑑定評価結果が大きく影響を与えます。
継続賃料の鑑定評価の詳細は別記事に譲り、ここでは結果に大きく影響を与えるファクターについて言及します。
直近合意時点
継続賃料の鑑定評価において最も重要なのが、「直近合意時点」という概念です。これは、当事者間(地主と借地権者)で賃料について合意があったと認められる直近の時点を指します。そして継続賃料の鑑定評価は、現行賃料に直近合意時点以後の事情変更を反映して継続賃料を試算する、という考え方で行われます。
例えば、不相当に低廉な水準の地代でも、更新契約等において一度合意してしまうとその直後に増額請求してもほぼ認められないことになります。地主側としては安易に低廉な水準の地代で合意せず、地道に交渉と増額請求を行うことが重要です。
継続賃料の鑑定評価は、原則として、直近合意時点から価格時点までの事情変更を考慮するものであり、直近合意時点は事情変更を考慮する起点となるものであるので、賃料改定の覚書、賃貸借契約書などの賃料改定に係る書面、賃貸借当事者の説明などから直近合意時点を適切に確定及び確認することが重要である。
不動産鑑定評価に関する実務指針(日本不動産鑑定士協会連合会)
「事情変更」の要素
事情変更の要素としては、地価水準や周辺賃料水準の変動、公租公課の変動といった経済的事由に加え、契約当事者間の恩恵的関係の解消(例えば地主・借地権者の一方に相続が発生した場合)といった要素も含まれます。こういった前提事実の有無を、両当事者が調停及び訴訟で主張することとなります。
ロジットパートナーズ法律会計事務所のサービス
当事務所は不動産鑑定士資格を有する弁護士が在籍しており、不動産の価格や賃料の評価についての紛争や訴訟に強みを持っています。
地代増額請求の事案に際しては、継続賃料についての不動産鑑定評価基準の記載や鑑定実務、周辺の土地価格の動向や地域要因・個別的要因を考慮した分析を行い、説得力をもった増額請求をサポートします。請求額の試算から当事者間の交渉、紛争対応(調停・訴訟)まで、網羅的に対応いたします。また、増額請求を受けた借地権者側の支援も可能です。
お気軽にお問合せください。